Yahoo!ニュース「日本の空き家400万戸時代へ すでに住宅戸数の1割以上が空き家の県も多数」
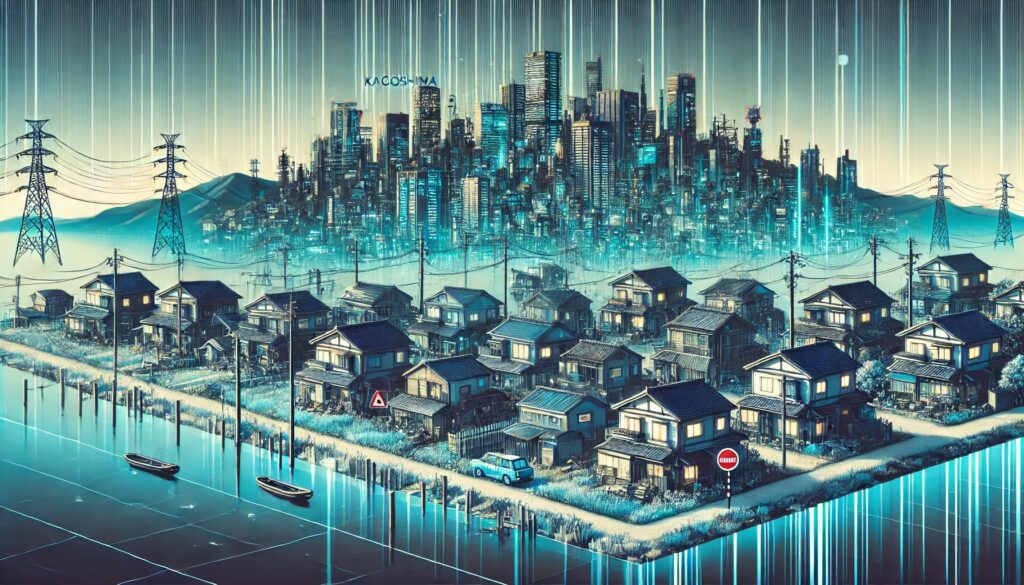
すでに日本の住宅の17戸に1戸が空き家
近年、日本各地で大きな社会問題として浮上しているのが、「空き家問題(※1)」です。
まず、どのくらいの数の空き家が日本に存在するのか、総務省統計局「令和5年住宅・土地調査」を通じて見てみましょう。2023年時点の日本の空き家(※2)は386万戸あり、この数は日本の総住戸数6,505万戸の5.9%に当たります。つまりすでに日本の住宅の17戸に1戸が空き家となっているのです。
空き家数は2003年の211万戸から、その後の20年間で1.8倍に増加しています。平均すると毎年8万7千戸の空き家が発生していることになります。
空き家増加による懸念点として、国土交通省は、防災性の低下、防犯性の低下 、ごみの不法投棄増加の恐れ、衛生の悪化、悪臭の発生の可能性、風景・景観の悪化などを指摘しています。
図表1.全国空き家数の推移

県別に見た空き家率の状況
では次に都道府県別の空き家率状況を見てみましょう。
最も、空き家率が高い都道府県は、鹿児島県で住戸の13.6%が空き家となっています。次いで、高知県、徳島県、愛媛県、和歌山県、島根県、山口県、秋田県と続きます。これらの県の空き家率はいずれも10%を超えており、10戸に1戸が空き家という状況です。このランキングを見てお分かりになる通り、九州や四国に空き家率の高い県が多いことが分かります。またこれらの県の高齢化率(65歳以上)は高く、全国平均(29.1%)の高齢化率を大きく上回っていることが分かります。
図表2.空き家率の高い都道府県

一方で空き家率の低い都道府県は、東京都を筆頭に神奈川県、埼玉県と首都圏近郊県が続きます。都市部の県が多いなかで第4位に沖縄県が挙がっているのは少し意外な感じがしますが、沖縄は日本で最も出生率が高い県であり、そのため住宅需要が高いことに加え、リゾート民泊として空き家を活用するケースも多いことから低い数値となっていることが考えられます。
図表3.空き家率の低い都道府県

図表2、3からもわかる通り、少子・高齢化や過疎化と空き家率には一定の相関が見られるようです。図表4は、都道府県別の高齢化率と空き家率を散布図にしてみたものですが、高齢化率の高い都道府県ほど空き家率が高いという傾向が伺えます。高齢化の更なる進展で、空き家の数が増えることは確実です。
図表4.高齢化率と空き家率の関係

過去のデータに基づき、2次関数の回帰分析を用いて今後の空き家数を予測してみると、
• 2030年:約 4,119,561戸(約412万戸)
• 2040年:約 4,236,564戸(約424万戸)
と2040年には約424万戸の空き家が発生することが予測されます。
空き家が増加している理由としては、以下のような理由が考えられます。
①人口減少・少子高齢化:日本の人口は2008年をピークに毎年数十万人のレベルで減少。また高齢化の進展により、持ち主が亡くなった家を相続する人が住まないケースが増加。
②地方の過疎化・都市部への人口集中:若者層の都市への人口移動により地域の過疎化が進行。住宅売却・賃貸環境の厳しい地方で空き家が増加。
③新築を好む文化:日本では住宅をリフォームして住むよりも、新築住宅を好むという根強い志向が存在。
④相続問題と管理の困難さ:相続した住宅が遠く離れていると、管理が困難になり放置されるケースもある。また相続登記が義務化されていなかったため、所有者不明の空き家が増加。(2024年4月から相続登記は義務化)
⑤法律・制度における問題:住宅が建っていると固定資産税が減額されるため、解体されずに放置されるケースがある。
空き家の増加をいかにして防ぐか
今後も予想される空き家の増加をいかにして防げばいいのでしょうか。そのためには、
<入口戦略>新たに発生する空き家の増加を防ぐ
<運用戦略>既存の空き家の再活用戦略を考える
<出口戦略>老朽化した空き家の撤去・解体を進める
の3つの方策に基づく具体的施策の実行が重要となります。
<入口戦略>については、国は
・相続登記の義務化:放置されることの多かった相続不動産の相続登記を2024年4月から義務化し、所有者不明の空き家の減少を図る。
・管理不全空き家に対する固定資産税優遇措置の適応除外
などを実施検討しています。
また<運用戦略><出口戦略>については、
「改正空き家等対策の推進に関する特別措置法」により、
・中心市街地や中山間地域など、空き家の集中するエリアでの活性化を促進する空き家活用特区制度の創設
・空き家の活用・管理に関わる相談を行う空き家等管理活用支援法人の指定
・空き家の活用、除却などに対する国や市町村からの一部費用補助制度
などを行っています。
このように国や自治体は、さまざまな規制強化策、活用支援策などを打ち出していますが、年間8万戸以上新たに発生する空き家解消の根本的な問題解決には至っていません。
総住宅戸数から言えば、もはや日本に新築住宅は必要ないのです。今後はいかに既存の建物を有効に再活用していくかという視点に軸足を移していかないと、不良空き家の増加を防ぐことは困難でしょう。
※1.2015年6月施行「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家等対策特別措置法)」では、「1年以上住んでいない、または使われていない家」を「空き家」として定義しています。
※2.ここでの「空き家」とは、賃貸・売却用の空き家や二次的住居、別荘等の空き家住宅を含まない「空き家」を指しています。
参考資料:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について」

