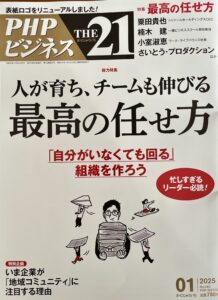第6回 センサー・サポート/モビリティ・アシスト
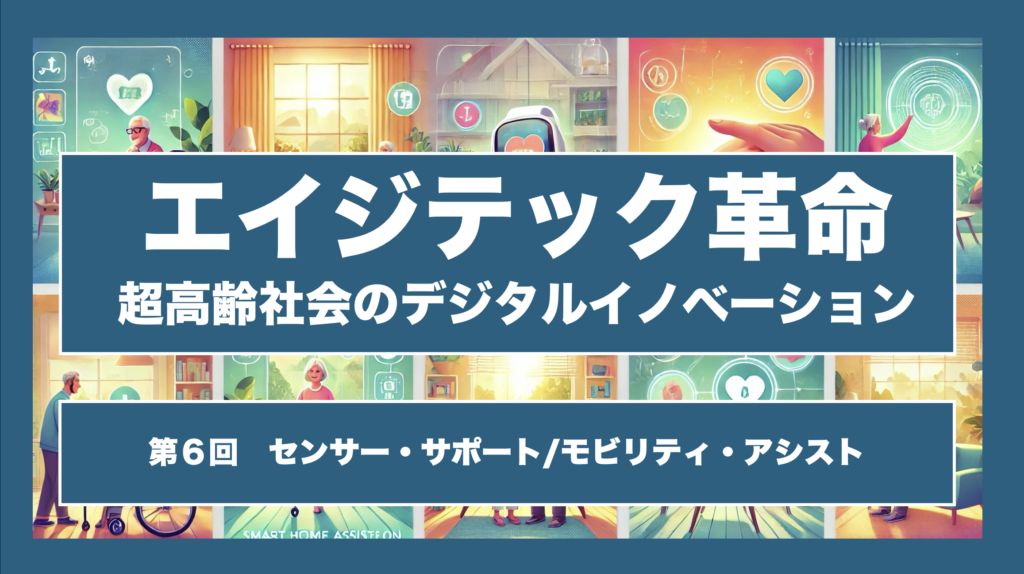
エイジテック革命、連載第6回のテーマは、センサー・サポート、モビリティ・アシストである。年齢とともに多くの人に訪れるのが、感覚器や運動器の機能低下、すなわち聞こえづらい(加齢性難聴)、視力低下、物忘れ(短期記憶)、歩きづらい(骨粗相症)などといった高齢者特有の疾患である。
高齢者の自立生活を支えるために、自分自身で見たり、聞いたり、歩けること、は大切である。こうした感覚器や移動器の補助としてのエイジテックがさまざまな領域で生まれている。視覚を補助する機器、聴覚を支援するテック機器などが手軽な価格で生まれている。移動するための支援機器として従来からあるのは車椅子であるが、これをさらにデジタルテクノロジーにより高度化したスマート車椅子、歩行サポートスーツといった移動を支える機器などが生まれてきている。
センサー・サポート
視覚障害者のためのAI音声認識デバイス
◾️オーカム(OrCam)
・社名:オーカム・テクノロジーズ(OrCam Technologies Ltd.))・設立:2010年・本社:エルサレム・イスラエル・共同ファウンダー、共同CEO:アムノン・シャシュア(Amnon Shashua)、ジブ・アビラム(Ziv Aviram)・URL:https://www.orcam.com/en/

オーカム・テクノロジーズは、弱視の方や視覚障害のある方のための視覚支援機器を開発するイスラエルのスタートアップである。同社の開発したウェラブル・デバイス、オーカム・マイアイ(OrCam MyEye)は、新聞や雑誌などさまざまなテキストを音声で読み上げてくれる。また目の前に見えるものの読み上げ、商品パッケージにある文字情報の読み上げ、顔認識機能による人の名前、紙幣の種類の読み上げなども可能である。
形状はレーザーポインターに似て、メガネのテンプル(つる)に取り付ける形で使用される。重量も22.5gなので軽量である。
認識したいものの方向を向き、声で「私の前に何がある?」と聞くと、デバイスは、「ドアがあります」と答えてくれる。また、本や雑誌などは、指をかざした周辺の活字を瞬時に読み上げてくれる。事前登録しておく必要はあるものの、最大100人の顔認識が可能で、登録した商品のバーコードを認識することで商品名を音声で教えてくれる。
同社の製品は、現在世界48ヵ国で使用されている。インターネットに接続の必要はないので、プライバシーが漏洩する心配も不要である。
同社の創業者は人工知能の権威であるアムノン・シャシュア氏とイスラエルで複数企業のCEOを務めたジブ・アビラム氏。自動運転支援システム(A D A S)の開発企業モービルアイ(Mobileye)を共同で設立した後、2010年にオーカムを設立した。(モービルアイは、その後イスラエル史上最高のIPOを果たし、2017年にインテルが買収を果たした。)
AIを活用した聴覚支援スマートフォンアプリ
■ハード・ザット(HeardThat)
・社名:シンギュラー・ヒアリング(Singular Hearing)・創業:2019年・本社:バンクーバー・カナダ・CEO:ブルース・シャープ(Bruce Sharpe)・URL: https://www.heardthatapp.com/
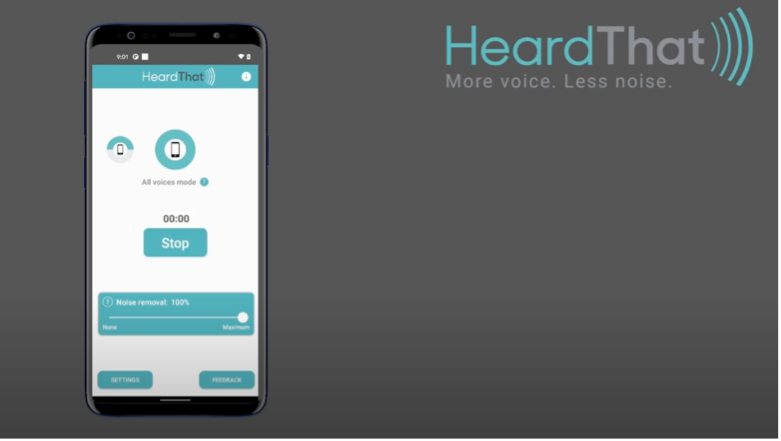
音声の聞こえずらさを解消するための補聴器は、性能向上を目的にさまざまな技術開発がなされてきた。一般的に人間の耳は、特定の声や音声を判別するために、脳内で自動的に必要とする音声を判別し、他の音はカットする選択的聴取(カクテルパーティ効果と呼ばれる)を行っている。しかし補聴器ではそうした選択ができないため、人為的に特定周波数帯の補正や増幅を行なったり、雑音を提言するノイズリダクション機能や、特定の話者の音声を最優先で聞き取るための指向特性などを備えることで、補聴性能を一歩ずつ前進させてきた。
しかし、シンギュラー・ヒアリング社が開発した聴覚支援スマートフォンアプリである「ハードザット(HeardThat)」は、そうした技術的バックボーンとは全く異なるアプローチで聞こえやすさを実現しようとするものである。
具体的な技術基盤はA Iによる深層学習である。A Iに多くの音声や多くのノイズ、雑音の中の多くの音声を聞かせることで、音声とノイズの違いを学習させる。何千時間にもわたる音声を通じて、A Iは何が音声で何がノイズであるかを自動的に識別できる水準に達する。そうした上で、ハードザットは、雑多な音声の中からノイズ部分を分離して廃棄し、明瞭度の高い音声だけ抜き取ることを可能としたのである。つまり他の補聴器は音をフィルタリングするのだが、ハードザットは音声と雑音をきれいに分離するのである。
加えて、ハードザットの技術は、補聴器といったハードウェアを伴うものではなく、スマートフォンのアプリとして提供される。現在のところ、このアプリは、将来的にはサブスクリプション・サービスとして提供される予定であるが、現在は期間限定の無料アプリとして提供されており、日本でもダウンロード可能となっている。(iOS,アンドロイドとも)
HardThatは、2020年6月にAARP Innovation Labsが主催したWhat’s Next Innovation Challengeで優勝を果たした。
創業者でありCEOのブルース・シャープ氏は、数理物理学の博士号を取得した後、バンクバー近郊の宇宙科学企業でキャリアをスタート。その後、コンピュータゲーム、コンテンツ管理、ビデオ制作など、さまざまな分野のソフトウェア新興企業で創業者や経営者として活躍したのち、近年ではAIや機械学習の世界に没頭し、これらの技術を使って聴覚支援のための製品を作るために2019年にSingular Hearing社を設立した。
モビリティ・アシスタンス
おしゃれなフランスのネットワーク型車椅子
◾️ニノ(NINO)
・社名: ニノ・ロボティックス(Nino Robotics)・創業:2011年・本社:スーべ・フランス・CEO:ピエール・バルディナ(pierre bardina)・URL:https://www.nino-robotics.com/en/nino-2/

ニノ・ロボティックス(Nino Robotics)が開発する車椅子ニノ(NINO)は、デザイン感覚に優れたフランスの企業だけあり、極めてカラフルで快適なデザインとなっている。一般的に機能とコストのみを重視したような無骨なデザインが殆どの日本社会の車椅子と比べると、その違いは歴然としている。
多様性が叫ばれる社会の中において障がい者のニーズは、殆ど置き去りになっている。そうした中で、モダン、カラフルで近未来的なニノのデザインは、車椅子に載るという行為そのものもワクワクした体験に変えてくれるに違いない。
ニノは電動車椅子であり、操作にも最新の自動安定化技術が採用されている。体幹の動きが良好な人であれば、体の前後の移動を車輪とセンサーが把握し、胸を前に動かすと前進し、後ろに動かすとブレーキや後進することができる。
またニノは、コネクテッド・ビークルでもある。スマートフォンやタブレットの専用アプリを通じてバッテリー残量、速度、走行距離などの情報を確認することができる。またニノのソーシャルシェアリング機能を使えば、撮影した写真やビデオを友人と共有し、楽しんでもらうこともできる。
また、同社にはもうひとつ、ニノワン(NINOONE)というユニークな移動支援機器もある。これは普通の車椅子に装着することで、電動ホイールに変身させることができるコンパクトなアタッチメント・ツールである。デザインもニノ同様にカラフルですっきりしたデザインであり、重量もわずか10キロ弱と軽量・小型なので、車や電車、飛行機にも手軽に載せることができるだろう。
手頃な価格の車いす移動センサー
■ブレイズ・モビリティ(Braze Mobility)
・社名:Braze Mobility Inc.・本社:Toronto ON・Co-Founder, CEO: プージャ・ビスワナタン(Pooja Viswanathan)・URL: https://brazemobility.com/

ブレイズ・モビリティは、車いすユーザーにナビゲーション・ソリューションを提供。同社が開発したのは車いすだと気付けない後方視界の注意喚起を促すためのブラインドスポットセンサーシステムである。車いすにこれを装着することで、見えない位置にある障害物を自動的に感知し、接触する前にライトやブザー音、振動などで警告を与得てくれるのである。距離の範囲は切り替えにより、近距離モードと遠距離モードでの選択が可能となる。
筋肉を補強するパワークロージング
■サイズミック(Seismic)
・社名:サイズミック(Seismic)・創業:2015年・本社:メロンパーク・カリフォルニア州・CEO:ロブ・パルフライマン(Rob Palfreyman)・URL:https://www.myseismic.com/

サイズミックが提供するアパレル、サイズミック・スーツは、作業現場での作業者の肉体的負担を軽減したり、体力や筋力が低下した高齢者の運動能力を補強するための筋肉補強ウェアである。同社では、このウェアをパワード・クロージングと呼んでいる。
サイズミック・スーツは、軽くて通気性のある袖のないボディスーツのようなウェアで、負荷の高い肉体作業の場合は作業着の上から(Seismic for Worker Safety)、高齢者の運動能力補強の場合は、洋服の下に装着して使用する(Seismic for Wellness)。いずれも筋肉の働きを代行するのではなく、必要な力の約15〜30%を補助することを目的とするものだ。
パワード・クロージングには、体の要所(腕や腰、太ももなど)に電気部品が配置されている。そこには電気信号で伸び縮みする人工筋肉と軽量アクチュエータが備えられており、着用者の体の動きや設定されたプログラムに応じ、それら人工筋肉が伸び縮みすることで、繰り返しのや長時間作業を行う際、体幹や腰を保護し、身体への負担や疲労を軽減するのである。例えば、着用している人が座っているか立っているかを自動認識し、動作に合わせたサポートや、長時間立っている場合、背中と腰を引き締め、より長く快適に立っていられるようにサポートしたりするのである。
スーツの動作データは、背中の根元にあるパックに搭載されたマイクロプロセッサーを通じてクラウドに送られ、着用者の危険な姿勢の頻度やタイミングなど、人間工学的、健康的、安全的に重要な情報が表示される。これにより、作業者の怪我防止や作業プロセスの改善に繋げることができ、高齢者の安全動作の確認などが可能となる。
元々このアパレルは、SRIインターナショナルが米国国防省の資金援助を受け、兵士の怪我のリスクを軽減し、持久力を向上させるために開発されたものだった。その後、この開発に関わったサイズミックの創業者であるリッチ・マホーニーが独立し、この技術の消費者市場での開発に取り組んだ。同社が現在ターゲットにしているのは、高齢化が進むベビーブーマー世代である。「年齢を重ねると体力が衰えてきますが、その団塊の世代はアクティブなライフスタイルを維持することに高い価値を見出しています」とリッチ・マホーニーは語っている。
現在、同社の製品はまだ市販化されていないが、初期設定とカスタマイズの費用、ソフトウェアのサポートなど全てをカバーする、レンタルサービスとしてご提供される予定である。
エアバッグで高齢者を転倒から守るスマートベルト
■タンゴ(Tango)ベルト
・社名:アクティブ・プロアクティブ(ActiveProtective)・創業:2014年・本社:Fort Washington PA・CEO:ワミス・シンガタット(Wamis Singhatat)・URL: https://www.tangobelt.com/

高齢期における大きな健康リスクのひとつが転倒である。予期せぬ場所での転倒がきっかけとなり、肘や腰を骨折し、数ヶ月にわたるリハビリが必要とされ、最悪の場合は寝たきりを余儀なくされる。
米国では毎年30万人以上が股関節を骨折し、そのうちの3分の1が負傷した年に亡くなるという。米国よりもさらに高齢化が進行する日本では高齢者の転倒リスクはさらに高いはずだ。
こうしたこともあり、エイジテックでは数多くの転倒関連のデバイスが開発されている。アップルウォッチに代表されるような、加速度センサーを備えたウェアラブル端末や、家庭内に設置したセンサーなどで転倒を感知。すぐさま家族や施設職員などに転倒を連絡するデバイスは、日本でも米国でも多数開発されている。しかしそれらの多くは、転倒したことを通知するという、あくまで事後対処的な装置である。即座の対応は可能でも、転倒した事実を変えることはできない。
それに対し、アクティブ・プロアクティブ・テクノロジーズが開発したタンゴ・ベルトは、転倒時の身体に与える衝撃を最小限に抑えるいわば人間版のエア・バッグである。腰に巻くこのタンゴ・ベルトを装着しておくと、転びそうになるとセンサーが反応し、膨らんだエア・バッグが腰を防御し、転倒時の骨折リスクを低減する。またそれと同時に介護者に対して、転倒したことを通知する。同時にモビリティ・データも収集しているので、活動レベルのモニタリング、物理療法の主要な指標の自動生成などが可能である。
タンゴ・ベルトを開発したのは共同創業者であり、外科医でもあるロバート・パックマン氏。彼は自分が治療した高齢者の転倒事故が多いことに心を痛め、ベルトのアイデアを思いつき、エンジニアであり起業家でもあるドリュー・ラカトス氏とともにアクティブ・プロアクティブ社を設立した。その後、3Dモーションセンサーやコールドガスインフレーターが安価となったことで、このアイデアを実用化することが出来た。現在、最初のベルトが生産ラインから出荷されており、いくつかの国の高齢者介護施設の入居者は約22ヵ月間パイロットベルトを着用している。
パイロットテスト中の短期リハビリセンターでの調査では、着用者の歩行距離が50%増加し、高齢者の転倒恐怖症を評価する調査では、恐怖症が軽減されるにつれ、使用者の自信の臨床評価が高くなったと報告されている。
タンゴ。ベルトは、リハビリ中やそれ以降も、より安全な移動を促し、股関節骨折を予防可能な状態にすることを目指している。