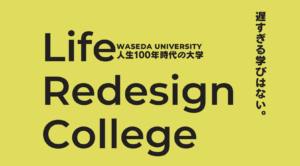Yahoo!ニュース「自分の死に時は自分で決めたい なぜリビング・ウィルの法制化は進まないのか」
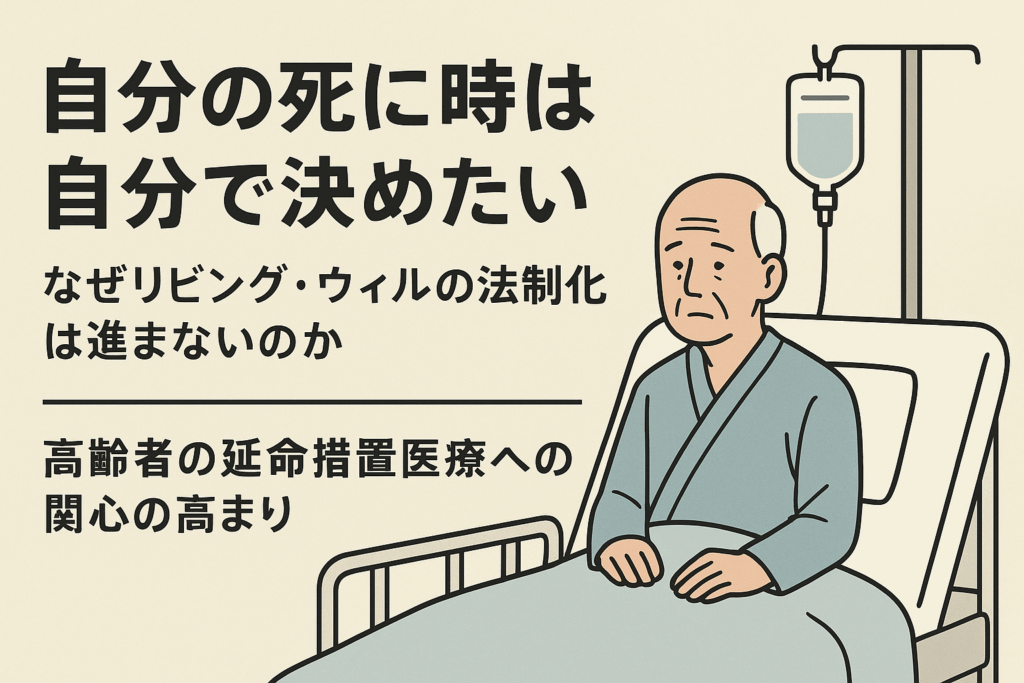
高齢者の延命措置医療への関心の高まり
先日の参議院総選挙の折に、参政党の党首は街頭演説で高齢者の延命治療の是非について言及し、「延命措置医療の医療費がかかりすぎている。90歳以上高齢者の終末期の延命措置医療費は全額自己負担化すべきである」と主張しました。(※1)
また、2022年に公開された日本映画『PLAN75』(倍賞千恵子主演、早川千絵監督)では、75歳以上が自ら生死を選択できる制度が施行された近未来の日本が描かれ、死の選択制度に翻弄される人々の姿が描かれ、話題となりました。
同映画では、制度施行の理由として、「高齢者増加による社会保障負担増」が暗示され、映画内CMでは、「未来を守りたいから(プラン75で自分の死に方を選定しましょう)」と高齢者に呼びかけました。
「90歳以上の高齢者の延命措置医療費は自己負担とすべき」
「75歳になれば、自分で死を選択できる権利が得られる」
これらは共に、「ディストピアな未来世界像」ですが、こうした言説や映画が登場した背景には、若い人々に、社会保障負担を巡る世代格差意識(高齢者の社会保障を現役世代が負担している)に対する不満や、終末期に関する自己決定意識(自分の死は自分で判断したい)が潜在的にあってのことでしょう。
前者(社会保障の負担格差)については現役世代が感じる意識でしょうが、後者(自分の死は自分で判断したい)については、現役世代のみならず、高齢者自身同様に考える人は多いでしょう。
自分の意思を伝えるリビング・ウィル(事前指示書)の存在
「もし、なにか事故や突然の病気で身体に異変や不具合が生じた際、もし、植物のような状態が長く続いたり、痛みや苦痛が続くのであれば、無用な延命措置は望まず、死なせて欲しい」
無用な延命措置を望まないと考える人が、生前に自分の意思を伝える方法として「リビング・ウィル(Living will)/事前指示書」があります。
リビング・ウィルとは、将来、自分が意思表示できなくなった時に受けたい治療や受けたくない医療をあらかじめ文章で示しておくものです。終末期や回復不能な状態を想定し、本人の自己決定を医療現場で尊重してもらうための道具です。
「リビング・ウィル」の条件としては、単に意思を記入しておけば事足りるというものではなく、まず、リビング・ウィルの定義と手続きが法的に整備された上で、決められた手順に従って準備する必要があります。
例えば、リビング・ウィルが法的に認められている米国オレゴン州「尊厳死法(DWDA)」(※2)のケースでは、
・18歳以上で余命6ヶ月以内の末期診断がなされていること
・主治医と独立医による二重診断が必要
・自己に意思能力があること
・2回の口頭請求(15日以上の間隔)+1回の書面請求(証人の立ち会いの下での署名)
などが尊厳死の条件として定められています。
近年、オランダ、ベルギー、スペイン、ポルトガル、韓国、米国(一部の州)、インドなど、海外ではリビング・ウィルが次第に法的に整備されてきています。
ただし、対象者は国により異なっており、「不治の病、余命数ヶ月の末期患者にのみ適応する国(韓国、インドなど)」と「不治の病に限定されず、法的に広く自己決定を認める国(ドイツ、スイス、英国など)」に大別されます。
高齢期の延命措置を望まないケースは後者に属することになります。
日本におけるリビング・ウィルの動き
日本で延命措置医療に関する自己決定権に関する議論は、この10年進みつつはあるものの、いまだ法制化には至っていません。
法制化がなかなか進まない理由としては、いくつかの理由が考えられます。
・個人の意思決定を重視する欧米諸国との文化土壌と比較して、日本は個人のみならず、家族や医師など血縁やオーソリティの意見が考慮される傾向がある
・法律による明文化を重視する欧米諸国に対し、あいまいさやファジーな要素を残したいと考える日本人の文化的側面がある
・一部には、法制化が安楽死の合法化につながるのではという懸念もある
そして何よりも、最も大きい理由は、社会的な合意形成がまだなされていないと国が判断しているからでしょう。
厚生労働省は、終末期医療のあり方に関して過去5回にわたって検討会を行なっています。(※3)
検討にあたっては、毎回、国民および医療介護関係者に対して、終末期医療に関するアンケート調査を行なっていますが、最も直近(平成22年)の調査結果では、リビング・ウィルの考え方に賛成の割合は増える傾向にあるものの、法制化については否定的な意見が一般国民では6割を超えています。法律で定めるよりも、その場その場の状況で医師や関係者と決めれば良いという意見が多く、個人の意思が尊重されるという社会的風土が今もなお続いている状況です。
日本版リビング・ウィルとしての「人生会議」
近年、厚生労働省は、「人生会議(アドバンス・ケア・プランニング)」という名称の下に、もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと話し合い、共有しようとする動きの啓発・普及を積極的に進めています。(※4)
これは先に述べた欧米のような「本人による意思決定」のみならず、「家族や関係者の理解と納得」が重要と考える日本型のリビング・ウィル合意形成に向けた試みと言えますが、合意内容の明文化が求められているものでもなく、結果として合意にファジーな要素が残ってしまいます。
終末期医療のあり方に関する検討会は、2010年を最後に開催されていません。
団塊世代が後期高齢期を迎える中で、今後亡くなる高齢者の数はさらに増加していきます。こうした人々が、自分の意思を反映した最後が迎えられるための環境づくりを改めて考え、整える時期になってきているのではないでしょうか。
(※1)2025年 北海道函館市での街頭演説において(2025年7月10日熊本日日新聞朝刊4面)
(※2)オレゴン州「尊厳死法(DWDA)」
(※3)厚生労働省 終末期の医療に関する懇談会https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127291.html
(※4)厚生労働省 人生会議してみませんかhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html