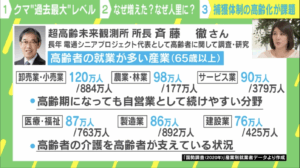コミュナルリビングの現代的意義

今から約5年前、放送大学大学院の修士論文として執筆したテーマが、「コミュナル・リビングの現代的意義」でした。コミュナルリビングとは、端的に言えば、家族や血縁関係によらず生活を共に暮らす住まい方の事を指します。かつての生活の基本単位は、「家族を基本とする世帯」でしたが、単身化や高齢者が進む中で、「家族」や「世帯」という単位が、例えば、家族メンバーがなんらかの形で困難に陥った場合のバックストッパーとして機能することが困難になってきています。そればかりか、例えばドメスティック・バイオレンスという言葉に象徴されるように、「家族」や「世帯」という仕組み自体が、日常の生活を脅かす事態もしばしば起きています。
そこで、本論文では、家族や血縁関係によらない共同的生活=コミュナル・リビングをもうひとつの暮らし方ととらえ、そうした住まい方の持続可能性を担保するためには、何が必要かを考えてみました。方法論としては、欧州、米国、日本における過去の共同生活の実態をスタディするとともに、それらの暮らし方に共通するものは何かを考えてみたものです。
この下に、口頭試問の説明の際使用したパワーポイントと、論文を貼り付けておきます。
(スマホからはダウンロードリンクになります)
ご興味のある方はお読みください。